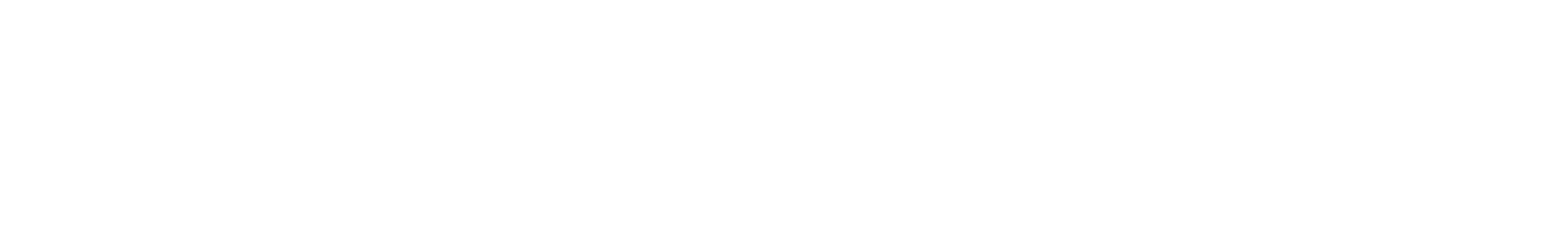就職活動に関しての雑感
以下はあくまで藤野の雑感であり、就職活動の壁にぶつかった時に「こういう考え方もある」という見方を提供している程度のものだと受け止めて欲しい。これでうまく行かなかったとしても責任は取れません
企業研究について
- 企業研究は、「その企業がどんな会社なのか」を知るために行うもの。そして、それは単にその会社が外に出してたり、リクルータが説明で出している情報を「集める」だけの作業ではない。情報を集めて、整理しまとめるというのは当たり前。その上で、例えば同業他社と比較してその会社の特徴を整理したり、インターンシップや見学会などで得た情報をもとに会社の潜在的な特徴を整理したりして、自分なりに「どういう会社なのか」を人に語れるようになるくらいまで「調べる・考察する」ことを企業研究という。
- 経営理念はその会社がどういう会社なのか、どういうことを大事にしているのかという会社の価値観を絵や言葉に表したもの。ただし、表向き綺麗事を言っているけど実態は違うこともよくある。一つの手がかりとしつつ、実際に企業見学会やインターンシップで見たり聴いたりしたことと整合するかを考えてみること。それが企業研究というものである。
- インターンシップや企業見学会で見たり聴いたりしたことは、そのこと一つ一つ自体が会社についての情報を与えてくれるものだが、表面的に見える情報だけではなく、それらをまとめて眺めてみて「どういう会社なのか」を自分なりに推察する。一つ一つをカードに書き出して、全体を整理してみるといい。その会社の雰囲気やポリシー、実態などが見えてくるはず。
志望動機
- 志望動機を考えるにあたっては、業界(業種)や職種を選んだ理由と、その会社を選んだ理由は基本的に分けて考えましょう。そして、志望動機は基本的に会社を選んだ理由を主に書くべき。その会社を自分が気に入った・選んだ理由を書く。特に第1志望や第2志望なら、そこをしっかり書けるくらいに会社のことを研究すること!
- 志望動機を考えるに当たり、「そこでなければならない理由」を考えようとするとしんどい。特別な事情がない限り、「この会社でなければならない」と考えているとすると、それは冷静さを欠いている状態(恋愛で片思いをこじらせている状態と同じ)。すこし頭を冷やした方が良い。実際には「別にそこまで『ここ以外は嫌』と思っているわけではないけど、まあでもここだと嬉しいな」という程度だろう。それくらいに思っておいた上で、「なぜここだと嬉しいな」と思うのかを考えよう。それが志望動機。
- 会社選択の時の話として、「福利厚生がいい」「給与がいい」「休日が多い」「残業が少ない」といのは選択の上で重要だろう。ただ、その辺がしっかりしているからと言って、それだけで仕事を選ぶとなると、結構危険。会社によっていろいろとカラーがある。業種や仕事内容が違うというのはもちろん、「上意下達で若手の間はノビノビとは仕事できない・叱られることが多い」や、逆に「若手から責任の大きい仕事を与えられるが、サポートは少なく放置気味。その仕事をこなすためのスキルは自己研鑽として身につけなければならない」という会社もある。自分がこの先長くその会社で働きたいと思っているなら「本当にこの会社で自分は長く働けるのだろうか?」と自問してみること。離職率などの客観情報は、会社の雰囲気(ブラックかそうでないか)を知る一つの手がかりかもしれないが、そもそもその会社の人たちと自分は上手くやれそうか、その会社の雰囲気についていけそうかを考えてみる。福利厚生が整っていても、自分に合わない会社や背伸びをして入った会社は、入ってから辛くなるよ。
- 例えば、業界No.1の会社の志望動機を書くときに、「安定してる・給料が良い・ネームバリューがある」は、本音ではあるだろうが、それを表にはかけないよね。なら、業界No.1ということが持っている意味や、なぜその会社が業界No.1なのかの理由を考えてみよう。業界No.1ということは自社の製品が広く世間で使われている(まあ、ニッチな業界でNo.1だと広く使われているとは言えないかもだが)ので、社会に与える影響が大きいわけで、社会にインパクを与える仕事も可能になる。あるいはNo.1であり続けるためには会社が常に努力し続けていたりしてるわけで、そういう社風というものがあるはず。そういったところと絡めて志望動機を考えるとよい。
- 志望動機で、「大学のゼミで学んだ知識が使えそう」というのは薄っぺらい。「では、そもそもなぜそのゼミを選んだのか?そのテーマを選んだのか」を突っ込まれる。実際のところは、ゼミ教員の人柄とかゼミの雰囲気とかで選んだ、というのはあるだろうが、全く違うテーマ・自分が興味のないテーマのゼミでも、その先生なら・その雰囲気ならそのゼミを選んだのか?例えば、広告論や生産管理論のゼミに今いたとして、同じような先生で同じような雰囲気の会計系のゼミを自分は選んでいたのか?そういったことを考えること。あるいは、最初はそうしたことだけでゼミを選んだとしても、「それを仕事で使いたい」と思うということはゼミ活動を通じてその分野に興味を持ったということだろうと、人事担当者は考える。なので、なぜ興味をもったのか?興味を持ったきっかけは?そういうことを考えてみる。もし、そういったことが見つからないなら「大学で学んだ知識を使えそう」と書くのはやめたほうがよい。
自己分析
- 上記のことをしようとすると、自分自身がどういう人間なのかをできるだけ深く知る必要がある。自己分析をキチンとすること。自分に得意なことはなにか、苦手なことはなにか、自分は「働く上で」何をポリシーとするのか。自分自身のこれまでの行動を振り返ってみて、自分自身の「譲れないもの」や「行動原理」を客観的に整理してみる。もちろん人に聴いてみるのもよい。ただ、考えても見えてこないこともある。そのときは「自分自身のポリシー」を今このタイミングで「決める」でも良い。自分自身が本当に心の底から納得でき、かつ自分の性格・性質と照らして、そのポリシーは無理なく体現できそうだというものに「決める」こと。「憧れ」とは切り離すこと。「そうありたい」という憧れを持つのは良いが、その憧れる存在に、本当に自分はなれるのか・なれるキャラなのか・なれる器なのか・努力できるのか、を見極めること。
- 説明会や求人票で企業が求める人材が書いてあったりするので、ありがちなのは「自分はまさにそういう人材です!」というアピール。ただ、忘れてはいけない。そもそも「社会人としてしっかりやっていける・嘘つきではない・信用がおける」という部分は言わずもがなの大前提として、求める人物像に含まれている。当たり前すぎて書いていないだけ。なので、求人票にある求める人材かどうかの判別以前に、この部分を企業は見ている。この部分がダメだと思われたら、その時点でアウト。なので、尚更「Who am I?」を自分の中で明確にし、自分自身の一本筋の通ったものを造り、自分に正直になっておく必要がある。
- 「自己分析ができない」という相談を受ける時に、よく言うのは「ぶっちゃけ、就職できればどこでも良い」という言葉。本当にそうだろうか?自己分析は色々な進め方・考える切り口があるが、一つ就職活動で大事なのは「自分はなにのために・だれのために・なぜ働くのか」を考えること。考えていくと、どんどん自分が薄っぺらい人間に思えてきて、落ち込んだりもするだろう。ただ、そうなるのは誰だって同じ。だってみんなはまだ働いたことがないんだもの。ただそこで逃げて(思考を辞めて)はいけない。それでも考え続けると、自分の中に「自分はどういう人間なのか」「なにをしたい人間なのか」という自分の軸が見えてくる。そこまで行けば、自己分析はできたもの。また、自分にあった仕事も見えてくる。そして、憧れてるけど自分にあってないな、という仕事も見えてきて諦めることができる。
人事担当者の目線
- 志望動機でも自己PRでも、「盛る」「飾る」はやってよいが「創る」はしないこと。教員が読んでも「創ったな」と分かる文章なんだから、何人も就活生を見てきている人事担当者が見ると尚更見抜かれる。
- 志望動機・自己PR・やってみたい仕事・大学で頑張ったこと、などいろいろと書かせられるが、人事担当者はそれをどう読むかというと、「別々に読んで個別に採点し、それらを合計して総得点を出す」とかしているわけではない。人の頭の造り的にも、項目毎に情報を区別なんでできない。頭の中では、それら全体を通して「この学生はどういう学生か」という人物像を描いている。書類選考では、そのイメージできる人物像から「この学生面白そう」と思ってもらえれば先に進むし、「この学生は違う」と思えば選考で落とされる。ただ、「イメージされた人物像が求める人材と違う」というように、明確に「違う」となって落とされるよりは(もしそうなら落とされる方が学生にとっても幸せ)、書かれていることから「その人物像がうまく描けない、どういう人なのか分からない」や「いってること・書いてることが一貫してない。本当にうちに心から来たいのか?」という場合の方が多い。当然ながらそういう人は,採用の中の優先順位は下になってしまう.なので、志望動機にしても自己PRにしても、活動についても、書くときには、エントリーシートなり履歴書なりの全体を読んだ人がどういう「自分像」を描くのかをチェックすること。これは書く上でのテクニックとしても重要だが、それよりも根本に「Who am I?」を考えることが大切。
- ちなみに、面接でも全体としての「人物像」を見られる。相手がキチンと書類を呼んでいる場合には、書類をもとに描いた人物像を一つの仮説にしながら、実際に話しをしてみて仮説を検証していくように質問を投げかけたり、語らせたりする。そうしてよりリアルな人物像を描く。読んでいない場合には、まさにその場でのやり取りを通じて、人物像を描く。そして、描き出された人物像を元に、「取りたい学生」の優先順位をつけていく。
- 面接は試験ではない。失点をしないように気を使うのは大切だが、相手が欲しいであろう人物像を勝手に忖度して、おもねって、それに合うように自分を偽ることのないように。そんなことで加点なんてされない。見抜かれるに決まってる。ありのままの自分をさらけ出すこと。本当に自己分析ができていれば、さらけ出すことの怖さも薄らいでくる。自信も出てくる。ただ、そこまでやっても「落とされる」ことはある。そこまでやって落とされるんだとしたら、それは仕方がない。最後は運が効いてくる世界もある。入試のように「テストの点が高い人」が通るのではない。例えば、すごくいい人でも、同じような人が去年入社していたら採用にならないのだ。たまたまその時に欲しい人材とマッチした人が通るのだ。これはどうしようもないこと。めぐり合わせ。仕方がない。なので、十分に全力を尽くして落とされたとしたら、それは運のせいにすればよい。また自然とそう思えるようになるはずだし、思いが届かなかったことの悔しさはあるものの「あの時ああしてれば」とか落ち込むこともなくなる。もし「あの時ああしてれば」という思考をしてしまってるとしたら、それはまだ自分の軸が見つかってない証拠。
- 会社側で面接をするときの方針は「相手の本性・能力を把握すること」である。そのために会社側がとる戦略は2つあり、一つは「語らせる」、もう一つは「表面を引き剥がす」である。特に、「表面を引き剥がす」ということについて、会社側も学生が就活マニュアル等で面接テクニックやよくある質問パターンへの回答を用意していることを把握している。そして、そうした準備されたものでは、学生は自分をよく見せるために「盛る・飾る」をしていることや、場合によっては「創る」もしていることを知っている。そこで会社側はそうした部分を引き剥がし、その学生の本性(本当はどういう人物なのか、どういうインテリジェンスを持っているのか、何をしたいのか(口で言っていることは本当にしたいことなのか))を把握するために、学生が用意をしていなさそうな質問(具体的には、その場での学生の回答に応じた質問)をしてくる。要するに何が言いたいかと言うと、特に人気のある会社においては、上辺だけの準備・就活テクニックだけで乗り切れるほど甘くはない。きちんと自己分析をし、自分が本当にしたいことや自分の適性など「自分」というものを十分に自覚し、どのような質問がきてもブレずに回答できるようにしておくことが大切である。
- 企業は最終面接やそれに近いところに行くほど、企業は「ふるい落とす」ではなく「優先順位をつける」ための面接をする。この違いとは、「ふるい落とす」ではある程度の基準をクリアすれば良いので準備(ESをキチンと書く、面接で減点されるようなことをしない等)をきちんとしてれば先に進むのはそれほど難しくない。一方で「優先順位をつける」では完全に他の人との競争となる。そして、面接ではテストのように点数をつけているわけではない。印象での勝負になる。となると、心情として「優先順位を上にしたい」と思わせる必要がある。つまり、キチンと自己分析をして軸を固めた上で、熱意を伝え「それだけうちの会社のことを好きになってくれてるのか」と感心させたり、「応援したい」や「一緒に働きたい」と思わせるような受け答えをすることが重要になる。つまり、人としての魅力が勝負の分かれ目になる。なので、面接の場で相手を魅了できるように、「人としての魅力」とはどういうことなのか、どういう言動・行動をする人に対して人は魅力を感じるのかをよく考えて、自分の「魅」力を高めよう(敢えて「魅」を強調してます)。
そもそも「働く」とは?社会人になるとは?
- 「お金が稼げればどこでもいい」という思考はまだまだ幼稚。もちろん「お金のことを考えるな」というわけではない。お金はみんなの仕事と社会の間をつなぐ架け橋であり、お金の先には社会がある。すなわち、お金は、皆さんが社会に対して何らかの「価値ある」仕事をした時に、その「価値」への対価として皆さんに返ってくるものである。なので、考えないといけないのは「自分が社会の誰に/どういうものにに対して/どういう場面で、どういう価値を提供したいか・どういう価値を提供できるのか」ということ。自分の軸が見つかっていれば、これを見つけらるのはそれほど困難ではないはず。逆に、自分の軸が定まってないと、ここで単に「キラキラした世界」への憧れだけで、自分の身の丈にあってないものや、自分に向いていないものを選んだりしてしまう。
- 皆さんは卒業すると「社会人」になる。それは単に大人・サラリーマンという意味ではない。「社会に対して仕事を通じて価値を提供する=社会からその価値に対する対価をもらう」という関係を築く(否が応でも築くことが求められる)人になるという意味です。なので、「社会」というもの十分に見据えて、なにのために仕事をするのかを考えて欲しい。