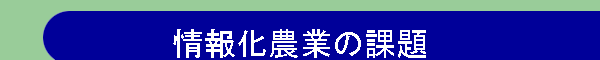(1) 農業の役割については国民共通の認識があります。
イ.消費者に安定して食糧を供給すること。
ロ.農業生産を通じて、その地域の産業振興を計ること。
ハ.その他、治山、治水、環境保全、教育等々です。
(2)農業と言う産業にコンピュータがどのような役割を果たせるか
イ.コンピュータの特徴を生かして生産者の所得を向上させる。
ロ.コンピュータを通じて生産者の意思決定を支援する。
ハ.その他、生産現場の事務処理を効率化する。
(3)それでは果たして、現場でコンピュータが目的を果たしているか
イ.メ ッ シ ュ 気 候
ロ.収 量 予 測
ハ.生 育 予 測
ニ.気象データ・ベース
ホ.出 荷 予 約
ヘ.市 況 情 報
私達はその他多くの農業関連のソフトウェアを開発してまいりました。
しかしながら残念なことに、あまり上手く運用されているとは思えません。
(4)その大きな原因は何か
一言で申し上げるならば当事者である農家の所得が目に見えて向上してはい
ない・・・ということにつきます。
例えば、メッシュ気候というソフトウェアについて言えばメッシュ気候という
ソフトそのものが開発目的であって、そのソフトウェアから得られた知見を使
って、例えば大根の生育予測をし、収量を予測し、病害虫の発生を適格に予知
し、その結果、安定した生産計画が立案され、出荷予測制度が確立され相対で
の有利販売に結びついて、結果として、農家の所得が向上した・・・という話
に結びつかなかったからであります。
決して、メッシュ気候というソフトウェアそのものに誤りがあったわけではな
く、農家の所得を向上させるための他の多くの要因が未整備である・・・とい
うことであります。
|