時代と学生のニーズに即した情報リテラシー教育
(1) 取組の概要
本学では設立(1992年)以来、情報リテラシー教育を学生の必要性に即したものにするべく改善を続けている。本学で現在実施している「情報リテラシー」教育は、技術的な能力である「コンピュータリテラシー」、社会的な能力である「ネットワークリテラシー」、コミュニケーション能力である「メディアリテラシー」の3つの柱から構成されている。これら3つの項目を必修科目である「情報科学」、「情報基礎演習」、選択科目である「情報処理」4科目、「プログラミング」4科目に配置している。
本学の学生は1年の前期に、図書館の使い方、タッチタイピング、日本語入力、ワープロ、電子メール、情報検索、HTMLによるホームページ作り、グループワークによる実践的なプレゼンテーション、を情報基礎演習で全員が学び、大学生活で最低限必要な「コンピュータリテラシー」を中心に身につける。そして1年後期には、情報社会の仕組み、インターネット、ネットワークリテラシー、メディアリテラシー、ハードウェアの仕組み、ソフトウェアの仕組み、ネットワークの仕組みを、情報科学でやはり全員が学び、「ネットワークリテラシー」や「メディアリテラシー」、さらにはコンピュータに関するより体系的な知識を身につけることができる。
「情報処理」としては、「表計算入門」、「データベース入門」、「Mac入門」、「表計算を使った統計処理」の4科目、「プログラミング」としては、「VBAによる汎用プログラム」、「Mathematicaによる自然・社会現象のシミュレーション」、「PerlによるCGI作成」、「Javaによるゲーム作成」の4科目を開講している。これら「情報処理」や「プログラミング」は選択科目で、学生は必要を感じたとき学年を問わずいつでも受講できる。
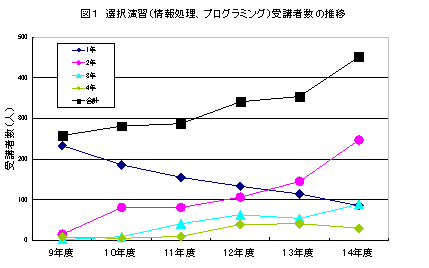
本学には、福井キャンパスと小浜キャンパスの2つのキャンパスがあり、生物資源学部海洋生物資源学科の学生40名は、2年生以降、小浜キャンパスで勉学に励むことになる。小浜キャンパスでも上記の選択演習が受講できるように、ネットワークを使ったネットワーク演習として一部の選択演習科目を開講する試みが行なわれている。
選択演習の受講者は年々増加し、図1のようである。本学の1学年の全定員が360名であることを考えると、延べ1学年の定員以上が選択演習を受講していることになる。
(2) 取組の内容と課題
本学では開学当初、1年前期に「情報科学」(講義)、「情報科学演習」、後期に「情報処理通論」(講義)、「情報処理演習」を必修で実施していた。しかし、1年のときに情報関係の科目が集中しすぎていて、2年生にコンピュータから離れる学生が多く3〜4年になると折角会得した使い方を忘れてしまうという問題点が各学部から指摘された。そのため、基本的な技能および知識のみ1年の時に「情報基礎演習」と「情報科学」で学び、後は必要に応じて受講できる「選択演習」を導入したカリキュラム改革を1997年度に実施し、現在も基本的枠組みとして継続している。
「情報基礎演習」は1年前期に開講されるが、4年間の大学生活に必要な基本的な項目を厳選し演習を実施している。この中では、コンピュータやネットワークの基本的な使い方だけでなく、図書館の使い方を本学図書館の司書に依頼して実施しているのが大きな特徴である。また、4〜5人のグループ単位で決めたテーマに関して新聞を作成し、それをクラス内で発表する総合演習を最後に課しているが、情報基礎演習で学んだ技術が実践的に使用できるということで、学生の評価は高い。
「情報科学」は1年後期に開講され、ユーザとしてコンピュータやインターネットを使う上で知っておいたほうがよい「情報リテラシー」に関する講義を行なっている。本学の学生に適した教科書で教育すべきとの観点から情報センター所属の教員3人が共同で1997年に「情報とコンピュータ」(森北出版)、2001年に「情報リテラシー」(森北出版)という教科書を執筆した。この教科書を使ってコンピュータやインターネットの仕組み以外に、インターネットを使う上でのマナーや注意点などのネットワークリテラシーや、インターネットを含むメディアからの情報を如何に読み解くかといったメディアリテラシーに関する項目も実施している。
選択演習は、学生は学年を問わず必要なときに受講できるが、前節で述べたように年々受講者数は増加している。選択演習で提供する内容は時代と学生の動向を見ながら少しずつ変更している。
開学以来、学生の必要性に即して毎年改善している情報リテラシー教育だが、今後以下のような方向性で改革していきたいと考えている。
(a)教科「情報」対応
2003度から高校で「情報」が始まり2006年度からの新入生は「情報基礎演習」程度の項目は既習であることが予想される。ただ、高校によって対応が違うとも考えられるので、2006年からの学生の到達度を見ながら、現実に即して変更していく。
(b)専門科目との連携
学生の視点からみると、基礎教育としての情報リテラシーと専門教育としての情報教育の連続性があることが望ましい。本学では、専門教育担当の教員がリテラシー教育担当の教員と共同して選択演習を行なう試みを2003年度から始める。
(c)コンピュータを用いない情報教育
情報を如何に探すかという点や、取得した情報を如何に評価するかという観点が、今後の情報教育では重要になると考えられる。情報科学の中で実施している「メディアリテラシー」や、情報基礎演習で行なっている「図書館の使い方」といったコンピュータを使わない情報教育も強化していく。
(d) eラーニングツールの利用
限られた教員で学生の必要性に即応した多様な情報リテラシー教育を行なうためには、教育を効率化する道具の導入も必要である。この観点から2002年度4月よりWebCTと呼ばれるeラーニングツールを基礎演習に導入しその評価を行なっている。今後はこういったツールにあったコース設計を行いつつ、より効果的な情報リテラシー教育を実現する必要がある。
(3)組織的対応について
情報リテラシー教育は本学では情報センターが担当しているので、前述のカリキュラム改革の決定プロセスは以下の通りである。まず情報センター教員が原案を作成したものを情報センター協議会において議論し、そこで了承されたら、次に一般教育協議会(現在は学術教養センター教授会)で他の一般教育カリキュラムとの整合性が確認される。 最終的には全学の委員が参加する教務委員会で議題として提出され、他学部カリキュラムと調整を図り、決定される。
本学には「新しい時代にふさわしい魅力ある大学」、「特色ある教育・研究を行なう個性ある大学」、「地域と連携し開かれた大学」という3つの基本理念がある。このなかの「特色ある教育」を実現するために、情報教育、語学教育、少人数教育、学際領域の教育に力を入れている。情報リテラシー教育は本学の特色ある教育を実現するための大きな柱であるということができる。
現在、情報リテラシー教育は、情報センター専任教員3名、他部局からの協力教員6名、他大学等からの非常勤講師3名の合計12名の教員で担当している。また、専任の職員2名、常駐のSEが1名、非常駐のSE若干名が、情報リテラシーで必要な情報機器やネットワークを管理運営して、いつでもよいコンディションで教育ができる環境を整えている。
情報リテラシー教育では主に情報センターにあるコンピュータ演習室を使って教育を行なっているが、演習室の機器は4年毎にリテラシー教育に即したものに更新されている。現在も来年度の更新に向けて、議論がされている最中だが、演習室混雑時でも自分のノートパソコンを持参すれば、ネットワークが利用できる無線LANシステムの導入や、時期選択演習に取り入れる可能性があるDTPソフト等の検討がなされている。
(4)取組実績について
図2 情報基礎演習が役にたつ点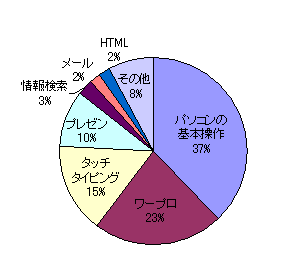
情報基礎演習では、タッチタイピング、ワープロ、HTMLによるホームページ作成、プレゼンテーションソフト、総合課題の計5つの課題を学生に課し、それらにより目標としたコンピュータやネットワークの操作がどの程度できるようになったかの教育効果を測定している。また、毎年終了時に学生にアンケートを実施し、情報基礎演習の教育プロセスが学生にとってどう受け取られたかを測定し、コースを改良する参考にしている。2002年度に情報基礎演習で行なったアンケートの結果のうち「どの演習項目が役にたつと思うか」の回答結果を図2に示す。
情報基礎演習は協力教員を含め6名の教員が9クラスの情報基礎演習を担当している。アンケートの結果を受け、担当教員で会議を開き、各教員が担当したコースの経験をふまえて、次の年の内容の詳細を決める。
選択演習においても課題の提出により個々の学生の教育効果を測定し、終了時アンケートによりそのコースがどのように学生に受け取られたかを測定するのは情報基礎演習と同じである。
2002年度から情報基礎演習と一部の選択演習で、eラーニングツールのWebCTを導入しているが、そのアクセスログを解析することにより、各学生の勉学の情況を把握し、コース設計の見直しの参考資料にできるのではないかと考えている。2002年度、福井キャンパスと小浜キャンパスで同じ選択演習を実施したが、福井では対面授業で小浜ではネットワーク授業の形態で行なった。この2つの選択演習のアクセスログを解析すると、対面とネットワーク演習では学生の勉学パターンが大きく違うことがわかる。また、ネットワーク演習での脱落パターンが当初の予想と大きくずれていたこともわかり、時期のコース設計の参考になった。
eラーニングツールのアクセスログから、そのコース内での学生の勉学パターンのデータが取れることは、そのコースの客観的な測定の可能性を示唆している。これまでそのコースでどのように学んだかは、学生へのアンケートに頼る他なかったが、アクセスログを利用することにより、アンケートとは違った観点からコースを測定できる可能性がある。
情報科学においては、二度の試験と一度のレポートにより、教育効果を測定している。さらに毎回の講義後に、質問、感想を各学生に提出してもらい、毎回の講義内容がどのように学生に理解されたかの測定をした。質問、感想の提出も以前は紙ベースで行なっていたが、2001年度から携帯のメールによりその場で質問、感想を提出してもらう形式に変更した。携帯での提出は、誰が提出したかの記録が残る点、過去の質問をすぐに検索できる点で大変便利である。質問が多かった項目は、次の講義で再度解説をしているが、その点は学生には好評であった。