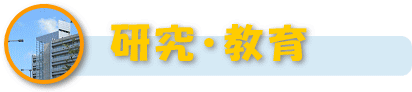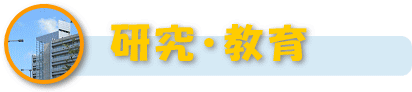| 研究室名 |
研究室の概要 |
水産資源生物学
研究室

|
私たちの研究室では、生理学・生態学・遺伝学をベースにそれらの境界領域的アプローチから、水産資源生物、主に沿岸魚類資源の増養殖と管理に関する教育研究を行っています。これらの研究は野外調査と室内実験を組み合わせながら行っていますが、2003年3月にオープンした本学海洋生物資源臨海研究センターを積極的に活用しています。
私たちの研究室は、特に春から夏にかけてはほとんど休みのない飼育実験や野外調査に開け暮れることになります。旺盛な体力と絶えることのない知的好奇心を保って、魚たちにも負けない健全な?日々が送れる学生に参加してほしいと思っています。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
青海忠久 |
海洋生物学
水産増養殖学 |
海洋生物学・魚類学 |
| 准教授 |
富永 修 |
資源生物学 |
水産資源学・生物資源統計学 |
| 講師 |
小北智之 |
生態学・進化生物学 |
資源育成学実習など |
|
海洋生物工学
研究室
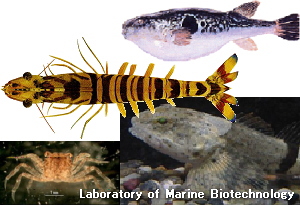
|
減少の著しい水産生物資源の維持管理と増養殖の発展、且つ海洋生物がもつ機能等を有効的に利用することを目指して、水産増養殖学および水族病理学を基礎として様々な基礎研究とこれに基づく技術開発を行っています。主に、甲殻類および魚類の繁殖機構の解明や、生理活性物質・免疫賦活物質を利用した飼料開発、魚介類のウィルス感染予防技術の開発や魚類の免疫系の解明に関する研究に取組んでいます。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
矢野 勲 |
甲殻類の繁殖生理学 |
海洋動物培養学・動物生理学・
水産増養殖学 |
| 教授 |
宮台俊明 |
魚類ウイルス学
魚類免疫学 |
水族病理学・一般微生物学 |
| 助教 |
田原大輔 |
魚類生理生態学
繁殖生理学 |
海洋生物工学実験 |
|
海洋生物学
研究室
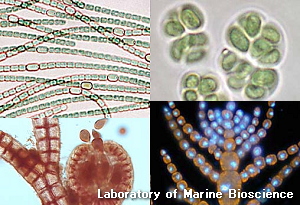
|
現代の生物学の歩みは,生物の営みを分子のレベルで見つめることから始まります。その姿勢は生物を私たち人間の資源として考え利用する場合にも欠かすことが出来ません。藻類は水の中の植物として水圏の生物すべての生活を支えています。私達の研究室ではそのような藻類の基本的な営みを,生理・生態・分子生物・生化学など様々な面から解析することを目指し,藻類の生き方を理解するための基礎知見の積み上げに少しでも貢献できるように努めています。具体的には,微細藻類(植物プランクトン)の独立栄養的生育の維持や窒素代謝系の生育環境による制御機構の分子生理学的解析、大型藻類(海藻)の生活史や生殖機構に関する細胞分子生物学的解析,藻類の進化・多様性に関する系統分類学的研究などテーマは多岐にわたっています。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
大城 香 |
植物生理学 |
藻類学概論・藻類生理学・
海洋生物学実験など |
| 准教授 |
神谷充伸 |
藻類学 |
分子生物学・海洋分子生物学・
海洋生物学実験など |
| 助教 |
吉川伸哉 |
藻類学
| 海洋生物学実験など |
|
海洋生態代謝学
研究室
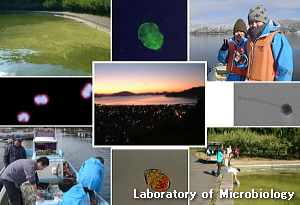
|
微生物は極めて小さく、その姿をとらえるには顕微鏡が必要なため、一見私たちの世界とは異質であるように思えます。ところが、個々は小さくとも、増殖して大きな集団となると、その水域に多大な影響を及ぼします。異常増殖して、生態系を乱したり、毒素を生産して環境問題を引き起こしている微生物もいれば、自然界の物質循環や生物生産を支える微生物もいます。私たちは、水域において赤潮・アオコの原因となる微生物や物質循環を担う細菌を中心に、その生理や生態を明らかにしようと研究しています。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
広石伸互 |
水圏微生物学 |
海洋微生物学・水域環境保全学など |
| 准教授 |
近藤竜二 |
微生物生態学
海洋微生物学 |
水域環境学・海洋環境微生物学実験など |
| 助教 |
高尾祥丈 |
|
海洋環境微生物学実験など |
|
海洋環境工学
研究室

|
本研究室は,小浜キャンパス唯一の物理系の研究室です。沖合や沿岸域,海岸や湖沼などの流れ,波,水質や底質などの海の環境を調べ,これを保全したり改善する方法を開発して,魚介類の住みやすい環境や美しい情緒ある海洋・海岸環境を創る研究を行っています。最近は,若狭湾の水深200m以深に存在する海洋深層水の動きが海底に棲む生物に与える影響を調べるために、海洋観測や、海の流れを再現可能な回転水槽を用いた実験を実施しています。これら一連の調査をもとに若狭湾のすぐれた漁場はどこにあるのか,新たな漁場をどこにどのように作ったらよいのか明らかにしていきます。また,若狭湾に点在する養殖場の環境を保全するため,適正な水質管理方策を講じることができるシステム作りに取り組んでいます。さらに,アサリや海藻が海の環境浄化に役立っていることを調べ,生物のもつ環境適応能力や浄化機能などを明らかにするための研究にも取り組んでいます。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
大竹臣哉 |
水産土木学
海洋生態系環境工学 |
大気海洋学概論・
海洋環境工学・構造力学 |
| 准教授 |
瀬戸雅文 |
水産土木学
海洋環境工学 |
水理学・沿岸海洋学 |
| 講師 |
兼田淳史 |
沿岸海洋学 |
海洋観測実習・環境工学実習 |
|
食品化学
研究室

|
食品化学研究室では、(1)海洋動物の細胞外マトリックス成分(主にコラーゲン)の基礎性状、食品機能および利用、ならびに(2)魚介類の流通過程における品質の変化に関する研究を行っています。
コラーゲンは、あらゆる多細胞動物の体内に存在するタンパク質で、食品中では主に食感の発現に関係しています。また、最近ではコラーゲンの持つ保水力に注目して化粧品の成分として利用されています。しかし、海洋動物のコラーゲンの中にはその基礎性状すら解明されていないものが少なくありません。それだけ未知の機能や利用の可能性が秘められており、今後の進展が大いに期待される分野です。また、魚介類は漁獲後利用されるまでの間に必ず時間的経過があり、その間に品質が変化します。しかし、その変化の詳細やメカニズムについては不明な点が多く、魚介類の味や食感の発現などの食品機能および食品としての安全性の観点から品質の変化を解明することは極めて重要です。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
横山芳博 |
水産化学 |
水産資源利用学・食品栄養学・
海洋分子生物学・食品化学実験など |
| 准教授 |
水田尚志 |
水産化学 |
生物資源分析化学・食品化学・食品化学実験 |
|
食品工学
研究室

|
日本人は古くから水産物を原料とする多種多様な食品を生み出してきました。現代人の多様な嗜好に対応した新しい加工食品を製造したり、あるいは未利用海洋生物資源の有効利用技術を開発するためには、伝統的な水産加工技術の基盤を科学的に解明し、水産物に含まれる各種の食品成分の貯蔵・加工中に起こる物理的、化学的あるいは微生物学的変化を制御するための基本原理を明らかにすることが不可欠です。食品工学研究室では、水産動物の筋肉の主成分である筋原繊維タンパク質と水溶性のエキス成分(遊離アミノ酸やペプチドなど窒素を含む低分子成分)を主な研究対象として、それらの貯蔵・加工中における変化を水産食品の味やテクスチャー(食感)および健康性機能との関連で研究しています。そして、これらの研究成果を水産食品の品質制御や加工技術の改良・開発に役立てることを目標としています。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
赤羽義章 |
水産利用学
食品保全学 |
基礎生化学・食品保全学・
資源利用学実習 |
| 教授 |
大泉 徹 |
水産利用学
食品生化学 |
食品工学・生体代謝機能化学・
食品工学実験 |
| 助教 |
伊藤光史 |
食品加工学 |
資源利用学実習 |
|
水産経営学
研究室

|
本研究室では水産業の経済及び経営と食品の流通に関する研究を行っており、当学科の中で唯一の社会科学系分野の研究室です。複雑な社会現象を分析する手法として重要なものは、経済・経営・流通の基礎的な理論と、実証的な「裏付け作業」です。そのため、他の自然科学の研究室の実験にあたるものとして調査や統計分析を重視しており、経済活動としての水産業や流通業を具体的な事実によって検証しつつ分析を進めるという方法を重視しています。 |
<スタッフ>
|
氏名 |
専門分野 |
主要担当科目 |
| 教授 |
加藤辰夫 |
食品流通 |
食品流通論・水産物流通調査・地域産業論 |
| 講師 |
東村玲子 |
水産経済学 |
水産経済学・国際漁業論・水産物流通調査 |
|